| 元素 | |
|---|---|
70Ybイッテルビウム173.0432
8 18 32 8 2 |
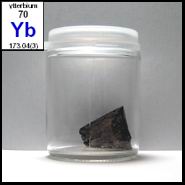
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 70 |
| 原子量 | 173.043 amu |
| 要素ファミリー | N/A |
| 期間 | 6 |
| グループ | 2 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 1878 |
| 同位体分布 |
|---|
168Yb 0.13% 170Yb 3.05% 171Yb 14.3% 172Yb 21.9% 173Yb 16.12% 174Yb 31.8% 176Yb 12.7% |
170Yb (3.05%) 171Yb (14.30%) 172Yb (21.90%) 173Yb (16.12%) 174Yb (31.80%) 176Yb (12.70%) |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 6.965 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 824 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 沸点 | 1193 °C |
ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |
イッテルビウム (Yb): 周期表元素
概要
イッテルビウム (Yb, 原子番号70) はランタノイド系列の14番目の元素であり、[Xe] 4f14 6s2という閉殻電子配置により特異な性質を持つ。この配置により+2酸化状態に異常に高い安定性を示し、ランタノイドの中で少数の二価化合物を容易に形成する元素の一つである。標準原子量は173.045 ± 0.010 uで、7つの天然安定同位体が存在する。隣接するランタノイドと比較して密度(6.973 g/cm³)、融点(824°C)、沸点(1196°C)が低い特性は、電子構造に直接起因する。工業用途は主にレーザー技術、原子時計、特殊冶金プロセスに集中している。
はじめに
イッテルビウムはランタノイド系列内で特異な位置を占め、典型的な希土類元素とは異なる化学的挙動を示す。14個のf電子による閉殻構造は、特にランタノイドでは珍しい+2酸化状態を安定化させる。この電子配置は化学反応性だけでなく物理的性質にも影響を与え、隣接元素と比較して密度や熱特性が顕著に異なる。常温で面心立方構造をとるが、これはランタノイドで一般的な六方最密充填構造とは対照的である。1878年にジャン・シャルル・ガリサール・ド・マリニャックによって発見されたイッテルビウムは、実験室の好奇心から精密計測や高出力レーザー技術で不可欠な元素へと進化してきた。
物理的性質と原子構造
基本原子パラメータ
イッテルビウムは原子番号70で電子配置[Xe] 4f14 6s2を持つ。完全に満たされた4fサブシェルは電子的安定性を高め、元素の化学的性質に深く影響する。原子半径は176 pm、Yb³⁺のイオン半径は86.8 pm、Yb²⁺は102 pmである。これらのイオン半径はランタニド収縮効果を反映するが、満たされたf殻によりその影響は緩和される。4f電子による遮蔽効果が小さいため有効核電荷が高くなり、元素の特異な性質に寄与する。第一イオン化エネルギーは603.4 kJ/mol、第二は1174.8 kJ/mol、第三は2417 kJ/molである。第二と第三イオン化エネルギーの大きなギャップはYb²⁺イオンの相対的安定性を示す。
マクロな物理的特性
新鮮なイッテルビウムは銀白色金属に淡い黄色がかった色調を示す。α、β、γの3つの同素体を持つ。常温で存在するβ型は面心立方結晶構造を持ち密度6.966 g/cm³である。-13°C以下で安定なα型は六方晶構造で密度6.903 g/cm³、795°C以上で存在するγ型は体心立方構造で密度6.57 g/cm³である。これらの密度値はツリウム(9.32 g/cm³)やルテチウム(9.841 g/cm³)と比較して顕著に低く、金属結合への閉殻電子構造の影響を反映する。824°Cの融点と1196°Cの沸点は金属中最小の液体温度範囲(372°C)を示す。300 Kでの熱伝導率は38.5 W/(m·K)、常温での電気抵抗率は25.0 × 10⁻⁸ Ω·mである。
化学的性質と反応性
電子構造と結合挙動
イッテルビウムの化学的挙動は[Xe] 4f14 6s2の電子配置によって支配され、+2と+3の双方の酸化状態を異常に容易に形成する。満たされたf殻は二価状態に特別な安定性を与え、Yb²⁺はアルカリ土類金属カチオンと多くの点で類似する。他のランタノイドが金属結合に3つの電子を供給するのに対し、イッテルビウムは2つの6s電子しか利用できないため、金属半径が増加し凝集エネルギーが低下する。主にイオン化合物を形成するが、有機金属錯体には共有結合性が現れる場合もある。配位数は通常6-9の範囲で、水溶液中では[Yb(H₂O)₉]³⁺のような九配位錯体が優先される。イッテルビウム化合物の結合長はイオン半径を反映し、八面体型配位でのYb-O結合距離は通常2.28-2.35 Åである。
電気化学的および熱力学的性質
イッテルビウムのパウリング電気陰性度は1.1、オールレッド-ロコウスケールでは1.06で、非常に電陽性な元素であることを示す。Yb³⁺/Ybの標準還元電位は-2.19 V、Yb²⁺/Ybは-2.8 Vである。これらの値は特に二価状態での強い還元性を反映する。電子親和力は約50 kJ/molで、金属的性質と一致する。第二から第三イオン化エネルギー(1174.8 → 2417 kJ/mol)の大きな増加は二価化合物への選択的安定性を示す。熱力学計算ではイッテルビウム(II)化合物は水溶液中で不安定であり、水を分解して水素ガスを発生することが判明している。Yb₂O₃の生成熱は-1814.2 kJ/mol、YbOは-580.7 kJ/molで、固体状態での三価化合物の優れた熱力学的安定性を示す。
化学化合物と錯体形成
二元および三元化合物
イッテルビウムはハロゲン化物を含む広範な二元化合物を形成する。三価ハロゲン化物YbF₃、YbCl₃、YbBr₃、YbI₃は全てランタノイド特有の構造を示し、YbF₃はタイソナイト構造、重い三価ハロゲン化物は六方晶UCl₃構造を取る。生成エンタルピーはフッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物でそれぞれ-1670、-959、-863、-671 kJ/molである。二価ハロゲン化物YbF₂、YbCl₂、YbBr₂、YbI₂はアルカリ土類金属ハロゲン化物と類似の蛍石型構造を持つが、高温で熱分解し3YbX₂ → 2YbX₃ + Ybの反応を示す。酸化物化学ではC型ランタノイド構造のYb₂O₃とNaCl構造のYbOが存在し、硫化物YbS、セレン化物YbSe、テルル化物YbTeも同様のパターンを示す。三元化合物にはガーネット構造Yb₃Al₅O₁₂やペロブスカイト誘導体YbAlO₃が含まれる。
配位化学と有機金属化合物
イッテルビウムの配位化学は二価・三価の双方の錯体を含むが、満たされたf殻により配位子場効果は最小限である。水溶液中では主に[Yb(H₂O)₉]³⁺の九配位錯体を形成するが、嵩高い配位子では低配位数が観測される。クラウンエーテルやクリプタンズはサイズ選択的配位により二価状態を安定化する。有機金属化学では(C₅H₅)₂Ybや(C₅H₅)₃Ybなどのシクロペンタジエニル錯体が存在し、各種合成反応の前駆体となる。ビス(シクロオクタテトラエン)イッテルビウムは特異な磁気特性を示す重要なサンドイッチ錯体である。ホスフィン、アミン、酸素供与配位子を含む混合配位子錯体は立体障害に応じた多様な幾何構造を示す。二価有機金属化合物は強力な還元性を持ち、炭素-炭素結合形成反応で有機合成に利用される。
天然存在と同位体分析
地球化学的分布と存在量
イッテルビウムは地殻に平均3.0 mg/kg (3.0 ppm)で存在し、スズ、鉛、ビスマスより多いが他のランタノイドより少ない。典型的なランタノイドの地球化学挙動に従い、火成岩中で分画結晶過程により濃縮される。主要鉱物は軽いランタノイドと比較して約0.03%を含むモナズ石[(Ce,La,Nd,Th)PO₄]、ゼノタイム(YPO₄)、ユーセナイト[(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)₂O₆]である。中国南部のイオン吸着粘土は経済的に重要な資源で、全希土類元素の0.05-0.15%を占める。一般的な造岩鉱物中での互換性は中程度で、部分溶融時の分配係数は残存相への濃縮を示す。風化過程では通常イッテルビウムが遊離し、粘土鉱物やリン酸塩鉱物への二次濃縮が生じる。
核特性と同位体組成
天然イッテルビウムは7つの安定同位体から成る:¹⁶⁸Yb (0.13%)、¹⁷⁰Yb (3.04%)、¹⁷¹Yb (14.28%)、¹⁷²Yb (21.83%)、¹⁷³Yb (16.13%)、¹⁷⁴Yb (31.83%)、¹⁷⁶Yb (12.76%)。最も豊富な¹⁷⁴Ybは核スピンI=0を持つが、¹⁷¹Ybと¹⁷³YbはI=1/2の核スピンを示す。これらの同位体特性はNMR応用や量子コンピューティング研究に重要である。32の放射性同位体が確認されており、¹⁶⁹Ybが最も長い半減期(32.0日)を持つ人工同位体である。この同位体は電子捕獲で¹⁶⁹Tmに崩壊し、63.1、109.8、177.2、307.7 keVのガンマ線を放出する。他の重要な放射性同位体には¹⁷⁵Yb (半減期4.18日) と¹⁶⁶Yb (半減期56.7時間) が含まれる。¹⁷⁴Ybの熱中性子断面積は69バーンで、原子炉内での放射性同位体生成を容易にする。
工業的生産と技術応用
抽出・精製方法
工業的生産はモナズ石やイオン吸着粘土の濃硫酸処理(200-250°C)から始まり、EDTAや類似のキレート剤を用いたイオン交換クロマトグラフィーで希土類元素を分離する。イッテルビウムの分離はランタノイド-配位子複合体の形成定数の微細な差を利用し、D2EHPAやトリブチルリン酸を用いた溶媒抽出が大規模生産で代替的に用いられる。精製過程では通常99.9%純度が達成される。金属製造は高真空下1000°CでYbCl₃をカルシウムまたはランタン金属で還元する方法が一般的だが、800°CでのYbCl₃-NaCl-KCl共晶混合物の電解法も代替法である。世界生産量は年間約50トンで、90%以上を中国が供給している。
技術応用と将来展望
現代のイッテルビウム応用は特異な核・電子特性を活かした専門技術分野に集中している。レーザー冷却された¹⁷¹Yb原子を用いる原子時計は10⁻¹⁹以下の周波数不確実性を達成し、578 nmの¹S₀ → ³P₀遷移を利用した高精度測定に貢献する。光ファイバーレーザー技術ではYb³⁺がシリケートガラスマトリクスの活性ドーパントとして働き、1030-1100 nm波長域で高出力連続波・パルス動作を可能にする。ポンプ光とレーザー光の量子欠陥(約6%)の小ささにより熱負荷が抑制され、キロワット級の高出力化が実現されている。量子コンピューティング研究では¹⁷¹Yb⁺イオンを電磁場に捕捉し、光学遷移による量子ゲート操作と状態制御に利用している。¹⁶⁹Ybは携帯型放射線撮影システムのガンマ線源として従来のX線発生装置に代わる選択肢となる。冶金用途ではステンレス鋼への微量添加による粒界制御や、圧電抵抗効果を利用した応力監視に応用される。
歴史的発展と発見
イッテルビウムの発見は1878年、スイスの化学者ジャン・シャルル・ガリサール・ド・マリニャックが鉱物エリウムから新成分「イッテルビア」を分離したことに始まる。この名称は発見地に近いスウェーデンの村イッテルビーに由来する。マリニャックはイッテルビアが未知の元素(後にイッテルビウムと命名)を含むと推測した。1907年、パリのジョルジュ・ウルバン、ウィーンのカール・アウアー・フォン・ヴェルスバッハ、ニューハンプシャーのチャールズ・ジェームズが独立にマリニャックのイッテルビアが2つの新元素を含むことを示し、元素発見史に転機を迎える。ウルバンは「ネオイッテルビア」(現代的イッテルビウム)と「ルテキア」(現代的ルテチウム)を分離したが、ヴェルスバッハはそれぞれ「アルデバニウム」「カシオペウム」と命名した。ウルバンとヴェルスバッハの間で命名権争議が生じ、1909年原子量委員会がウルバンの命名を採用した。イッテルビウム金属の最初の相対的に純粋な単離は1953年、マンハッタン計画中に開発されたイオン交換精製技術を用いて達成された。その後の数十年で二価酸化状態の安定性と先端技術応用が徐々に明らかになった。
結論
イッテルビウムは4f¹⁴閉殻電子配置によりランタノイド系列内で特異な地位を占め、+2酸化状態の異常な安定性が物理・化学的性質全てに影響を与える。低い密度・融点・配位特性は希土類元素とは一線を画し、量子コンピューティングや高精度測定技術への応用を可能にする。今後の研究課題には効率的な分離技術の開発、量子特性の応用拡大、高出力レーザー技術の進展が含まれる。限られた天然存在量と複雑な抽出プロセスにもかかわらず、新興技術分野での重要性は今後も継続すると予測される。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
