| 元素 | |
|---|---|
39Yイットリウム88.9058522
8 18 9 2 |
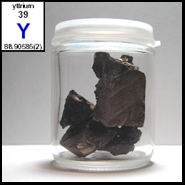
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 39 |
| 原子量 | 88.905852 amu |
| 要素ファミリー | 遷移金属 |
| 期間 | 5 |
| グループ | 2 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 1794 |
| 同位体分布 |
|---|
89Y 100% |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 4.469 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 1526 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 沸点 | 3337 °C |
ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |
イットリウム (Y): 周期表の元素
要旨
イットリウム (Y, 原子番号39) は周期表第3族に属する銀白色の遷移金属で、原子量88.906 u、電子配置[Kr] 4d¹ 5s²を持つ。この元素は主に三価の性質を示し、安定なY³⁺化合物を形成し、ランタノイドに類似した顕著な化学的性質を示すが、dブロック元素である。自然界では唯一の同位体⁸⁹Yとして存在し、地殻中で希土類鉱物と関連して31 ppmの存在量を持つ。工業的意義は蛍光体技術、レーザーシステム、高温超伝導体、先進セラミックスへの応用に由来する。この元素は優れた熱安定性を示し、保護性酸化皮膜を形成し、遷移金属と希土類元素の化学を橋渡しする特異な性質を示す。生産は混合希土類鉱石からの複雑な分離プロセスを経て行われ、年間約7,000トンのイットリウム酸化物が世界中で利用されている。
はじめに
イットリウムは周期表において第五周期dブロックの最初の元素として特異な位置を占め、ランタノイド系列に化学的性質が近いが、同族のスカンジウムとは異なる。電子配置[Kr] 4d¹ 5s²により三つの価電子を持ち、Y³⁺イオンの無色性はd・f電子の非対性による。1789年にヨハン・ガドリンがスウェーデンのイッテルビーで発見したイッテルビット鉱石から確認され、希土類化学発展に歴史的意義を持つ。ランタノイド収縮効果により、ガドリニウムとエルビウムの間のイオン半径を示し、重希土類元素との共存を説明する。現代応用は熱安定性、光学特性、電子特性を活かし、省エネ照明から量子材料研究まで幅広い技術に利用されている。
物理的性質と原子構造
基本原子パラメーター
自然界の⁸⁹Y同位体は原子番号39、39個の陽子と50個の中性子を含む。電子配置[Kr] 4d¹ 5s²によりd¹遷移金属とされるが、三価電子の完全放出によりdブロック典型とは異なる化学挙動を示す。原子半径は約180 pm、六配位環境でのY³⁺イオン半径は90.0 pmで重希土類イオン半径と一致する。内殻電子による遮蔽効果が顕著で、ランタノイド類似の化学性質を生む。⁸⁹Yの基底状態は核スピン量子数I = 1/2、磁気モーメントμ = -0.1374核磁子で、NMR分光分析で重要となる。
マクロな物理的特性
常温で六方最密充填構造をとり、格子定数a = 364.74 pm、c = 573.06 pm。遷移金属典型の金属結合を示し、298 Kでの密度4.472 g/cm³、熱膨張係数10.6 × 10⁻⁶ K⁻¹。融点1799 K (1526°C)、沸点3609 K (3336°C)で顕著な熱安定性を示す。融解熱11.4 kJ/mol、蒸発熱365 kJ/molで強い金属結合を反映。比熱容量0.298 J/(g·K) (298 K)。銀白色の金属光沢を示し、293 Kでの電気抵抗率596 nΩ·mで中程度の導電性。熱伝導率17.2 W/(m·K)で、他遷移金属と比較し中程度の熱伝導性。
化学的性質と反応性
電子構造と結合挙動
化合物は主にイオン結合性を示し、典型dブロック元素の共有結合性とは異なる。d¹配置によりY³⁺化合物では[Kr]貴ガス配置を達成するため価電子が完全放出される。+3酸化状態が支配的だが、特殊環境下で+2・+1状態も観測される。配位数は6-9が典型で、結晶化合物では八配位構造が特に多い。有機金属錯体ではカルボラニル配位子とのη⁷ハプティシティや制御環境下での安定な金属-炭素結合を示す。ルイス酸性質は中程度で、Y-O結合エネルギー約715 kJ/mol、Y-F結合エネルギー670 kJ/mol。
電気化学的・熱力学的性質
パウリングの電気陰性度1.22で、典型dブロック元素より低くアルカリ土類金属と同等。三段階のイオン化エネルギーは+3状態形成を示す:第一イオン化エネルギー600 kJ/mol、第二1180 kJ/mol、第三1980 kJ/mol。電子親和力はほぼゼロで金属性を反映。標準水素電極に対する標準還元電位E°(Y³⁺/Y) = -2.372 Vで強い還元性と水溶液中でのY³⁺安定性。Y³⁺の水和エンタルピー-3620 kJ/molで水分子との強い相互作用。化合物格子エネルギーはイオン半径と相関し、Y₂O₃は15,200 kJ/mol、YF₃は4850 kJ/mol。
化合物と錯形成
二元・三元化合物
最も安定な二元化合物は立方体構造バイクバイタイトのY₂O₃で、2683 Kまで熱安定。両性特性を持ち強酸で溶解してY³⁺水和錯体を形成、高温下で濃アルカリと反応。三ハロゲン化物YF₃、YCl₃、YBr₃は473 K以上で直接反応形成、高い融点とイオン性。三元化合物にはY₂O₂S(蛍光体応用)、天然ゼノタイム中のYPO₄、還元条件でのYC₂、Y₂C、Y₃Cカルビド相があり、アセチリドYC₂は炭化カルシウム類似の水反応性。
配位化学と有機金属化合物
酸素供与配位子(アセチルアセトン、シュウ酸、EDTAなど)との広範な錯形成。Y³⁺の大きなイオン半径により配位数8・9が典型で、四角反プリズムや三帽三角プリズム構造が観測される。水溶液中では速水和交換を示す[Y(H₂O)₈]³⁺錯体形成。有機金属化学では嵩高い配位子による安定化されたシクロペンタジエニル誘導体YCp₃やアルキル錯体を含むが、高酸素親和性のため無酸素条件が必要。注目すべき例として+2酸化状態のビス(シクロオクタテトラエニル)イットリウムやη⁷ハプティシティカルボラン錯体がある。触媒応用ではオレフィン重合・水素化反応で陽イオン活性種形成を促進。
天然存在と同位体分析
地球化学的分布と存在量
地殻存在量31 ppmで43番目に豊富な元素。鉛、錫、水銀を上回る。重希土類元素と類似したイオン半径・電荷半径比により、火成・熱水プロセスでの分留パターンが一致。土壌濃度は10-150 ppm(乾燥重量平均23 ppm)、海水は9 pptで炭酸緩衝液中での低溶解性を反映。アポロ計画の月岩サンプルは地球玄武岩より高濃度で、月形成時の分化蓄積プロセスを示唆。堆積岩(頁岩平均27 ppm)、花崗岩40 ppm、玄武岩20 ppm。熱水変質と風化プロセスにより二次鉱物・イオン吸着粘土に濃縮される。
核的性質と同位体組成
自然界では⁸⁹Yのみ(存在比100%)で、22の単同位体元素の一つ。39陽子・50中性子(魔法数)で核安定性を示す。核磁気共鳴活性核はスピンI = 1/2、磁気モーメントμ = -0.1374 μₙで⁸⁹Y NMR構造解析可能。人工同位体は32種(質量数76-108)が合成されるが半減期は極めて短い。最安定人工同位体⁸⁸Yは半減期106.629日で、⁸⁹Yの中性子照射または⁸⁸Sr崩壊で生成。医療応用の⁹⁰Yは半減期64.1時間で最大βエネルギー2.28 MeVの純β⁻崩壊により⁹⁰Zrへ。核断面積は⁸⁹Y(n,γ)⁹⁰Y反応で熱中性子捕獲断面積1.28バーン、共鳴積分1.0バーン。
工業生産と技術応用
抽出と精製方法
工業生産はバストネサイト、モナザイト、ゼノタイム、イオン吸着粘土鉱石から開始。濃硫酸・塩酸による酸浸出で希土類を溶解し、選択的沈殿と再溶解サイクルでトリウム・鉄などを除去。イオン交換クロマトグラフィーで陽イオン交換樹脂に希土類塩化物・硝酸塩を吸着し、イオン半径差と錯形成挙動で分離。溶媒抽出ではトリブチルリン酸やジ(2-エチルヘキシル)リン酸をケロシン希釈液に用い、pH制御下で有機相への選択抽出。シュウ酸イットリウムY₂(C₂O₄)₃·9H₂O沈殿後、1073 Kで焼鈍し99.999%高純度Y₂O₃を得る。金属生産は減圧下でカルシウム・マグネシウム合金による無水YF₃の還元(1873 K以上)、アーク炉での再溶解で金属スポンジ生成。
技術応用と将来展望
最大用途は蛍光体応用で、省エネ照明のランタノイド活性化剤マトリクスとして利用。セリウムドープY₃Al₅O₁₂:Ce³⁺は白色LEDの主発光体で、青色発光を150ルーメン/ワット超の広スペクトル白色光へ変換。高出力固体レーザー(波長1064 nm)にネオジムドープNd:Y₃Al₅O₁₂が利用され、産業カット・溶接・医療応用。高温超伝導体YBa₂Cu₃O₇-δは液体窒素沸点超の93 K臨界温度を達成し、送電ケーブル・磁気浮上・SQUIDに応用。先進セラミックスでは、熱バリアコーティング・酸素センサー・固体酸化物燃料電池に酸化イットリウム安定化ジルコニアを採用。新興応用には熱安定性とサイクル寿命を向上させたリチウム鉄イットリウムリン酸塩電池、量子ドット技術、イットリウム・ガドリニウム合金の磁気冷凍システム。
歴史的発展と発見
1787年、カール・アクセル・アーレニウスがスウェーデンのイッテルビー鉱山で異常に重い黒色鉱石(当初はタングステン含有と誤判しイッテルビットと命名)を発見。1789年、ヨハン・ガドリンが初めて未知の地球酸化物(イットリア)を確認し、最初の希土類酸化物発見となる。1797年、アンドレアス・グスタフ・エケベルグがイットリア命名を確立(ラボアジエの元素概念未確立)。1828年、フリードリッヒ・ヴェーラーがカリウム還元法で金属イットリウムを単離(不純物混入)。1840年代、カール・グスタフ・モーサンダーが粗イットリア中に複数の希土類酸化物を発見し、テルビウム・エルビウムを分離。イオン交換クロマトグラフィー発展(1940年代)まで純粋化合物生産は遅れた。20世紀中盤の電子構造理論・X線結晶構造解析で遷移金属と希土類の間の特異位置が解明。技術革命は1960年代の⁹⁰Y医療応用、カラーテレビの蛍光体、1987年の高温超伝導体発見に続く。
結論
イットリウムは周期表でdブロックとfブロックの化学を橋渡しする特異な位置を占め、電子構造と熱的・化学的安定性によりエネルギー効率照明から超伝導材料まで多様な技術応用を可能にする。量子技術・持続可能エネルギーシステムの発展により、光学・電子・磁気特性を精密制御した新素材需要が拡大。今後の研究は新規イットリウム量子材料開発、ドープカソードによる蓄電池技術向上、単原子触媒の配位化学探求。グリーン技術(蛍光体変換LED、高温超伝導体)の発展に伴い、グローバル持続可能性イニシアチブのキーコンポーネントとしての地位を確立。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
