| 元素 | |
|---|---|
100Fmフェルミウム257.09512
8 18 32 30 8 2 |
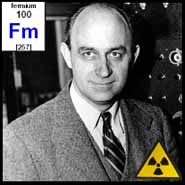
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 100 |
| 原子量 | 257.0951 amu |
| 要素ファミリー | アクチノイド |
| 期間 | 7 |
| グループ | 2 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 1952 |
| 同位体分布 |
|---|
| なし |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 9.7 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 1527 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 化学的性質 | |
|---|---|
| 酸化状態 (あまり一般的ではない) | +3 (+2) |
| 第一イオン化エネルギー | 6.498 eV |
セシウム (Cs) 3.894 ヘリウム (He) 24.587 | |
| 電子親和力 | 0.350 eV |
ノーベリウム (No) -2.33 Cl (Cl) 3.612725 | |
| 電気陰性度 | 1.3 |
セシウム (Cs) 0.79 F (F) 3.98 | |
| 原子半径 |
|---|
フェルミウム (Fm): 周期表元素
要旨
フェルミウム (Fm, 原子番号100) は、軽元素の中性子照射によって合成可能な最重量元素として特異な位置を占める合成アクチノイド元素である。1952年の初水素爆弾実験の爆風で発見され、主に+3酸化状態を示し核安定性が限られている。最も安定な同位体257Fmは100.5日の半減期を持つが、他の同位体は著しく短い崩壊期間を示す。フェルミウムの化学的性質は、有効核電荷の増加によりアクチノイド前段元素より強い錯形成能を示す。現在の応用は核研究に限られ、生産量の少なさと放射性崩壊の制約により実用化は進んでいない。
はじめに
周期表で原子番号100に位置するフェルミウムは、中性子捕獲合成法でアクセス可能な最終元素である。この合成アクチノイドは超重元素化学と核物理学の理解に基本的意義を持つ。電子配置[Rn]5f127s2によりアクチノイド系列に属し、fブロック特性を示す一方、超ウラン元素特有の核不安定性が顕著である。核反応の先駆者であるエンリコ・フェルミに因んで命名され、フェルミウムの発見は超重元素研究における重要な節目となった。天然存在限界を超える位置にあるため、高強度中性子源や粒子加速器を備えた専門施設での人工合成に限られている。
物理的性質と原子構造
基本原子パラメータ
フェルミウムは原子番号100で電子配置[Rn]5f127s2を持ち、5f軌道に12個の電子を配置する。理論計算と隣接アクチノイドとの比較から原子半径は約1.70 Åと推定される。Fm3+のイオン半径は約0.85 Åで、アクチノイド系列におけるランタノイド収縮効果を反映する。価電子に作用する有効核電荷は軽いアクチノイドより著しく増加し、結合特性と錯体安定性の強化に寄与する。スペクトロスコピー研究は5f12配置と一致するエネルギーレベル構造を示すが、試料の限界と短半減期により詳細な原子スペクトルは未解明が多い。
マクロな物理的特性
フェルミウム金属はバルク量での単離が未達成であり、マクロな物理的性質の直接測定は不可能である。理論予測では重アクチノイドに典型的な面心立方構造を持ち、密度は約9.7 g/cm³と推定される。アクチノイド系列の傾向から融点は約1800 Kと予測される。フェルミウム・イッテルビウム合金の昇華熱測定からは298 Kでの142 ± 42 kJ/molの値が得られている。磁化率測定は未対電子5f軌道による常磁性を示唆するが、理論モデルでは金属的性質を示すものの、実験的検証は試料の限界と放射性崩壊により困難である。
化学的性質と反応性
電子構造と結合特性
フェルミウムの化学的性質は、主に+3酸化状態の安定性を示すアクチノイド特性を呈する。5f12電子配置により水溶液中で12個の未対電子を有し、常磁性と特異な分光特性を示す。還元条件では+2酸化状態も可能で、Fm3+/Fm2+の電極電位は標準水素電極対比で-1.15 Vと推定される。この還元電位はイッテルビウム(III)/(II)と類似し、二価状態の中程度の安定性を示す。フェルミウム錯体は主にイオン結合性を示すが、有効核電荷と収縮したイオン半径により軽アクチノイドより共有性が強化される。
電気化学的・熱力学的特性
電気化学的測定ではFm3+/Fm0の標準還元電位が-2.37 Vと判明し、フェルミウムが極めて陽イオン性であることを示す。Fm3+イオンの水溶液中での水和数は16.9で、酸解離定数は1.6 × 10-4 (pKa = 3.8) である。これらの値は軽アクチノイドより強い電荷密度を反映し、金属-配位子相互作用の強化を示す。逐次イオン化エネルギーはアクチノイドの予測傾向に従い、第1イオン化エネルギーは約627 kJ/molと推定される。有効核電荷の増加により軌道半径の収縮と結合エネルギーの増大が全電子配置で生じる。
化合物と錯形成
二元・三元化合物
フェルミウム化合物は試料量の微少性と放射性の制約から溶液化学に限られている。フェルミウム(II)塩化物 (FmCl2) はサマリウム(II)塩化物との共沈法で確認されており、唯一の固体二元化合物である。酸化条件ではFm2O3の安定性が示唆される。ハロゲン化物錯体はアイスシュテインやカリホルニウム類似体より安定性が増大し、有効核電荷効果が原因とされる。水酸化物はpH上昇で生成し、酸解離測定に基づくpH 3.8以上で沈殿する。
配位化学と錯形成
フェルミウム(III)は酸素・窒素配位子との安定な錯体を形成する。α-ヒドロキシイソ吉草酸との錯形成は軽アクチノイドより強化され、クロマトグラフィー分離に利用される。塩化物・硝酸塩錯体はカリホルニウムやアイスシュテインより形成定数が増大する。水溶液中での配位数は通常8-9で、大イオン半径の要件と一致する。EDTAやDTPAなどの有機キレート剤はFm3+の高電荷密度により極めて安定な錯体を形成し、放射化学処理における分離・精製に不可欠である。
天然存在と同位体分析
地球化学的分布と存在量
フェルミウムは全ての核種が極めて短半減期で、地球地殻には安定同位体が存在しないため天然には存在しない。仮に地球形成時に存在しても完全に崩壊した。約20億年前のガボン共和国オクロの天然核反応炉で中性子捕獲により一時的に存在した可能性があるが、現在は残っていない。地上でのフェルミウム生成は核反応炉・粒子加速器・核実験による人工合成に限られ、環境中では核実験後の大気中でフェムトグラム~ピコグラムレベルの極微量が検出されるに留まる。
核特性と同位体組成
質量数241-260の20の同位体が確認されている。最も安定な257Fmはα崩壊による100.5日半減期で253Cfに変換する。重要な他の核種には255Fm (t½ = 20.07時間)、254Fm (t½ = 3.2時間)、253Fm (t½ = 3.0日) が含まれる。257Fmより重い同位体はマイクロ秒~ミリ秒半減期で自発核分裂を起こし、「フェルミウムギャップ」が中性子捕獲による超重元素合成を制限する。核特性は軽同位体でα崩壊優勢、重同位体では自発核分裂が顕著となる。中性子捕獲断面積は質量数増加に伴い急減し、合成効率を制約する。
工業生産と技術応用
抽出・精製方法
フェルミウム生産は軽アクチノイドの中性子照射による高輝度研究炉での合成が主流である。オークリッジ国立研究所の高輝度同位体炉 (HFIR) が主要生産源で、キュリウムやバークリウム標的の中性子捕獲により数ヶ月の照射でピコグラム単位を生成する。生産量は原子番号増加に伴い指数関数的に減少し、257Fmは年間ナノグラム未満に限られる。核実験では歴史上より大量の生成が可能で、1969年のハッチ実験では10 kgの爆風から4.0 pgの257Fmを回収したが、全体の生産量の10-7という極めて低い回収効率であった。
技術的応用と将来展望
現在のフェルミウム応用は基礎核物理学・化学研究に限定されている。超重元素特性研究では理論モデル検証と分光技術開発のベンチマークとして利用される。核構造研究では「安定の島」近傍の殻効果・崩壊機構の探求に用いられる。将来の応用として中性子源・医用同位体生成が提案されるが、実用化には生産効率の大幅改善が必須である。改良された炉設計や新核反応による合成法の進展が応用研究の拡大を促す可能性がある。
歴史的発展と発見
フェルミウムの発見は1950年代初頭のマナハッタン計画の水素爆弾開発に端を発する。1952年11月1日の「アイビー・マイク」水爆実験の爆風分析でアルバート・ギオルソらカリフォルニア大学バークレー校のチームが7.1 MeV α崩壊と20時間半減期から255Fmを確認した。冷戦期の安全保障上の理由から発見は1955年まで公表されず、1954年にはスウェーデン研究者によるイオン照射法での独立合成もあった。エンリコ・フェルミの業績を称えて命名され、中性子捕獲による最重量元素合成の実証と超重元素研究の幕開けとなった。
結論
フェルミウムは中性子照射合成可能な最終元素として周期表の重要な位置を占め、バルク生産の実用的限界を示す。その特異な核特性と化学的挙動はアクチノイド化学と超重元素物理学の基礎的理解を提供する。軽アクチノイドより強化された錯体安定性と電気化学的特性は、最重量アクチノイド特有の有効核電荷効果を反映している。現在は合成量と放射性不安定性により基礎研究に限られるが、理論モデル検証と核科学技術発展のための基準元素として継続的に重要である。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
