| 元素 | |
|---|---|
67Hoホルミウム164.9303222
8 18 29 8 2 |
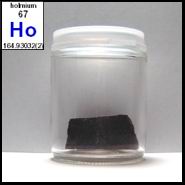
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 67 |
| 原子量 | 164.930322 amu |
| 要素ファミリー | N/A |
| 期間 | 6 |
| グループ | 2 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 1878 |
| 同位体分布 |
|---|
165Ho 100% |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 8.795 g/cm3 (STP) |
H (H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 1470 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 沸点 | 2720 °C |
ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |
ホルミウム (Ho): 周期表の元素
要約
ホルミウムは周期表の67番目の元素であり、卓越した磁気特性と特異な分光特性を示す。この希土類金属は自然界で最も高い磁気透磁率と磁気飽和特性を持ち、19 K以下の温度で特異な強磁性挙動を示す。ランタノイド系列の11番目の元素として位置付けられ、電子配置 [Xe] 4f11 6s2 に典型的な三価化学を示す。元素はレーザーシステム、磁極子、原子炉制御システムにおける重要な技術的応用を持つ。地殻中の天然存在度は1.4 ppmと限られ、主にイオン交換プロセスによりモナザイト鉱石から商業的に抽出される。ホルミウム化合物は特徴的な黄色と分光吸収特性を持ち、光学キャリブレーション標準に利用される。
はじめに
ホルミウムはランタノイド系列内で特異な位置を占め、自然界で最も強力な磁気特性を発揮する。周期表第6周期に属しジスプロシウムとエルビウムの間に位置し、11個の不対4f電子を持つ重ランタノイドの典型的電子構造を示す。その磁気モーメント10.6 μB は自然界で最大値を記録する。発見は1878年にジャック=ルイ・ソレとマルク・ドゥラフォンテン、ペル・テオドール・クレーヴェが共同で行い、酸化イットリウム鉱石の分光吸収線を観測することで確認した。元素名はストックホルムのラテン語名Holmiaに由来し、スウェーデンでの発見を反映している。相対的な希少性と希土類元素との分離困難にもかかわらず、高磁場システム、レーザー技術、原子炉制御における産業的意義が顕著である。
物理的性質と原子構造
基本原子定数
ホルミウムは原子番号67で電子配置 [Xe] 4f11 6s2 を持ち、4fおよび6s部分殻に13個の価電子を配置する。原子半径は176 pm、三価イオン半径Ho3+ は八面体配位で90.1 pmである。有効核電荷計算では内殻電子による遮蔽効果が顕著で、ランタノイドの特性を反映する。4f11 配置により最大の軌道角運動量結合を生じ、基底状態項記号は 5I8 となる。三価酸化状態の安定性を反映し、逐次イオン化エネルギーは第一イオン化エネルギー581 kJ/mol、第二イオン化エネルギー1140 kJ/mol、第三イオン化エネルギー2204 kJ/molである。第四イオン化エネルギーとの顕著な増加は四価状態での4f10 配置の安定性を示す。
マクロな物理的特性
純粋なホルミウムは明るい銀白色金属光沢を持ち、重ランタノイドに典型的な比較的柔らかい機械的特性を示す。標準条件では六方最密充填構造に結晶化し、格子定数a=357.73 pm、c=561.58 pmである。密度は室温で8.795 g/cm3 に達し、原子量164.93 uの重さを反映する。融点は1734 K (1461°C)、沸点は2993 K (2720°C) で、イッテルビウム、ユーロピウム、サマリウム、ツリウム、ジスプロシウムに次ぐ第6に揮発性の高いランタノイドである。融解熱は17.0 kJ/mol、蒸発熱は265 kJ/mol、298 Kにおける定圧比熱容量は27.15 J/(mol·K)である。金属は常温で常磁性を示し、キュリー温度19 K以下で強磁性秩序に転移する。
化学的性質と反応性
電子構造と結合挙動
ホルミウムの化学反応性は電気陽性な性質に由来し、パウリング電気陰性度1.23から化合物形成にイオン性が顕著である。4f11 電子配置によりf軌道の結合への関与は最小限で、6s2 および1個の4f電子を放出して安定なHo3+ 配置を形成する。配位化学では配位数6〜12が一般的で、[Ho(OH2)9]3+ のように9配位の水和錯体を形成する。d軌道の不在によりπ逆配位能が不可能で、有機金属化学はイオン性シクロペンタジエニルおよび単純アルキル化合物に限定される。4f電子と配位子軌道の軌道重なりの悪さにより共有結合寄与はごくわずかである。
電気化学的および熱力学的性質
Ho3+/Hoの標準還元電位は標準水素電極に対して-2.33 Vで、ランタノイドに典型的な強い還元性を示す。逐次イオン化エネルギーは三価状態の安定性を反映し、第一イオン化エネルギー581 kJ/mol、第二イオン化エネルギー1140 kJ/mol、第三イオン化エネルギー2204 kJ/molである。電子親和力は約-50 kJ/molの負値を示し、安定な電子配置を持つ金属元素の特性を反映する。ホルミウム化合物の熱力学的安定性は格子エネルギーと水和エンタルピーと相関し、高電気陰性元素とのイオン結合化合物形成を好む。水溶液中での酸化還元挙動は広範なpH域で+3酸化状態の安定性を示し、強アルカリ条件でのみ水酸化ホルミウム沈殿を生成する。
化学化合物と錯形成
二元および三元化合物
ホルミウムは典型的ランタノイド化学量論パターンに従う多様な二元化合物を形成する。Ho2O3 は最も安定な酸化物で、日光下では黄味がかり、蛍光灯下ではピンクに変色する特性を持つ。この酸化物は空間群Ia3̄の立方晶バイスバイ石構造を持ち、約2700 Kまで熱安定性を示す。ハロゲン化物にはHoF3 (ピンク結晶性固体)、HoCl3 (YCl3型層状構造の黄色潮解性結晶)、HoBr3、HoI3 (黄色結晶性物質) が含まれる。カルコゲナイド化合物は単斜晶構造のHo2S3 および6 K以下の反強磁性を示すHo2Se3 を含む。形成反応は高温下での直接元素結合または酸化ホルミウムと酸の置換反応で進行する。
配位化学と有機金属化合物
配位錯体は高配位数と硬質配位子への好配位性を示す。水溶液化学では速い水分子交換動力学を伴う九配位の[H2O)9]3+ 種が支配的である。遮蔽された4f軌道により配位子場効果は最小限で、電子スペクトルは鋭いf-f遷移が支配的である。一般的な配位幾何構造には三帽三方柱および歪八方反角柱配置が含まれる。EDTA、ジケトン、カルボン酸などのキレート配位子はエントロピー駆動プロセスで安定な錯体を形成する。有機ホルミウム化学は立体障害配位子で安定化された[Ho(C5H5)3] のようなイオン性シクロペンタジエニル化合物と単純アルキル誘導体に限定される。遷移金属に典型的なカルボニルおよびオレフィン錯体形成はπ逆配位能の不在により制限される。
天然存在と同位体分析
地球化学的分布と存在度
地殻中のホルミウム存在度は質量比で1.4 ppmで、タングステンと同程度の希少性を持つ。奇数元素の一般的傾向に従い、隣接する偶数元素ジスプロシウムとエルビウムより存在度が低い。主要鉱物は約0.05%のホルミウムを含むモナザイト (Ce,La,Nd,Th)PO4、ガドリニサイト (Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10、およびゼノタイムYPO4である。中国南部のイオン吸着性粘土が主な商業資源で、全希土類含有量の約1.5%を占める。風化プロセスは選択的溶解と吸着によりホルミウムをlateritic鉱床に濃縮する。海水中濃度は400 ppqと極めて低く、大気中存在は実質的に無視できる。
核特性と同位体組成
天然ホルミウムは安定同位体165Hoのみで構成され、モノアイソトピック元素である。核特性には核スピンI=7/2と磁気双極子モーメントμ=-4.173 μNが含まれる。理論予測では161Tbへの極めて遅いα崩壊が存在するが、半減期は1020年以上で実験観測未達である。人工同位体は質量数140〜175をカバーし、163Hoは電子捕獲崩壊で4570年の半減期を持つ。準安定状態166m1Hoは約1200年の半減期を持ち、複雑な崩壊スペクトルによりガンマ線分光器キャリブレーションに利用される。熱中性子吸収断面積は165Hoで64.7バーンに達し、原子炉制御システムの燃焼可能な中性子毒として利用可能である。
工業生産と技術的応用
抽出および精製方法
商業的ホルミウム生産はモナザイト濃縮物の酸溶解およびトリウム除去後にイオン交換分離技術を適用する。隣接ランタノイドとの分離にはイオン半径と錯生成挙動の微小差を利用したクロマトプロセスを必要とする。ホルミウムを吸着した陽イオン交換樹脂はα-ヒドロキシイソ吉草酸でpH制御下に溶離され、隣接元素に対する分離係数1.5〜2.0を達成する。代替法には選択的沈殿法と有機リン酸抽出剤を用いる溶媒抽出法がある。金属生産は不活性雰囲気下で無水HoCl3またはHoF3をカルシウムで還元後、減圧蒸留精製を行う。年間世界生産量は約10トンで、分離の複雑さと需要の少なさから1キログラムあたり約1000ドルの価格が維持される。
技術的応用と将来展望
主要応用は高磁場永久磁石の極片製造における卓越した磁気特性の活用で、高飽和磁化と透磁率により磁場を増強する。ホルミウムドープYIG (Ho:YIG) は2.1 μm波長の固体レーザーに使用され、腎結石破砕や前立腺手術などの医療用途に展開されている。光学応用では分光光度計の波長キャリブレーション標準として酸化ホルミウム溶液の特徴的な鋭い吸収線を200〜900 nmスペクトル域で利用する。核応用では高熱中性子吸収断面積を活かし、反応度制御のための燃焼毒性物質として原子炉制御システムに導入される。新興応用には単原子磁気状態を活用する量子コンピュータ研究、単原子ビット記録を達成するデータ記憶システム、ホルミウム感光性ランタノイドナノ粒子を用いるNIR-II生体イメージングが進展している。
歴史的発展と発見
ホルミウムの発見は1878年、スイス化学者ジャック=ルイ・ソレとマルク・ドゥラフォンテンがエルビウム含有物質の分光吸収線に異常を観測したことに始まる。スウェーデンのペル・テオドール・クレーヴェによる独立した単離研究は、ランタノイド硫酸塩の系統的分画結晶化により新元素の存在を確認した。クレーヴェの方法論はカール・グスタフ・モーザンダーが開発した技術を用い、エルビア (エルビウム酸化物) の徹底精製により「ホルミア」(褐色) と「ツリア」(緑色) の2つの分画を取得し、それぞれホルミウムとツリウムの酸化物であることを示した。語源はストックホルムのラテン名Holmiaにちなみ、クレーヴェの所属機関への敬意を表している。純粋な酸化ホルミウムの単離は1911年まで待たれ、金属ホルミウムの製造は1939年にハインリッヒ・ボマーのカルシウム還元法に依った。ヘンリー・モーズリーのX線分光研究では試料のジスプロシウム混入により原子番号66の誤判定を受けたが、後続の化学分析で正しく識別された。電子構造と磁気特性の現代的理解は20世紀の量子力学と固体物理学の進展により築かれた。
結論
ホルミウムは希少ながらも卓越した磁気特性を備えるランタノイド元素で、高磁場マグネットシステムから量子コンピュータ研究まで多岐な重要な役割を果たしている。天然最大の磁気モーメント、特異な光学特性、中性子吸収特性の結合により、21世紀技術における医療レーザー、量子デバイス、先進材料科学の応用拡大が予測され、その重要性は増大しつつある。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
