| 元素 | |
|---|---|
78Pt白金195.08492
8 18 32 17 1 |
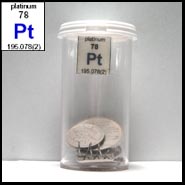
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 78 |
| 原子量 | 195.0849 amu |
| 要素ファミリー | 遷移金属 |
| 期間 | 6 |
| グループ | 1 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 600 BC |
| 同位体分布 |
|---|
192Pt 0.79% 194Pt 32.9% 195Pt 33.8% 196Pt 25.3% 198Pt 7.2% |
192Pt (0.79%) 194Pt (32.90%) 195Pt (33.80%) 196Pt (25.30%) 198Pt (7.20%) |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 21.46 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 1772 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 沸点 | 3827 °C |
ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |
| 化学的性質 | |
|---|---|
| 酸化状態 (あまり一般的ではない) | +2, +4 (-3, -2, -1, 0, +1, +3, +5, +6) |
| 第一イオン化エネルギー | 9.017 eV |
セシウム (Cs) 3.894 ヘリウム (He) 24.587 | |
| 電子親和力 | 2.125 eV |
ノーベリウム (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| 電気陰性度 | 2.28 |
セシウム (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
白金 (Pt):周期表の元素
要旨
白金は卓越した化学的不活性と腐食抵抗性を示し、現代化学において最も重要な貴金属の一つとして位置付けられている。原子番号78、原子量195.084 uで周期表10族に属し、−2から+10までの多様な酸化状態を示す。この元素は自動車排ガス制御システムや石油精製プロセスを含む多くの工業プロセスで顕著な触媒特性を発揮する。結晶構造は面心立方格子を採用し、密度21.45 g/cm³は一般的な金属を大幅に上回る。天然の白金は主に硫化物含有鉱石中の原生鉱として産出し、世界の埋蔵量は南アフリカのブッシュフェルド複合体とロシアのノリリスク地域に集中している。
はじめに
白金は周期表で原子番号78の位置を占め、電子配置[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹によって特徴づけられる。この電子配置は白金の卓越した安定性と化学抵抗性に寄与する。白金は白金族金属(PGMs)に属し、類似した化学的性質と地質学的産出パターンを持つ。白金の発見は前コロンブス期の南米文明に遡るが、1748年にアントニオ・デ・ウロアが正式に記載するまで18世紀になってから体系的な研究が始まった。金属半径は1.39 Å、酸化状態に応じてPt²⁺で0.86 ÅからPt⁴⁺で0.77 Åまで変化するイオン半径を示す。これらの物理的特性は直接的に配位化学と触媒特性に影響を与える。
物理的性質と原子構造
基本原子パラメータ
白金の原子構造は[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹の電子配置を持ち、6s軌道の有効核電荷は10.38、5d軌道は8.85の値を示す。第1イオン化エネルギーは870 kJ/mol、第2イオン化エネルギー1791 kJ/mol、第3イオン化エネルギー2800 kJ/molと続く。これらの値は強い核引力を反映し、白金の化学的安定性に寄与する。金属状態での原子半径は1.39 Å、共有結合半径は1.36 Åである。電子親和力は−205.3 kJ/molの負の値を示し、電子の付加が不利であることを示唆する。核磁気特性には6つの安定同位体があり、¹⁹⁵Ptは核スピンI = 1/2を持ち、33.83%の天然存在比を占める。
マクロな物理特性
純白金は光沢のある銀白色外観を示し、延性と展性に優れている。金属は常温で面心立方構造(Fm3m空間群)に結晶化し、格子定数a = 3.9231 Åである。融点は2041.4 K (1768.3°C)、標準大気圧下での沸点は4098 K (3825°C)に達する。融解熱は22.175 kJ/mol、蒸発熱は469.9 kJ/molである。298.15 Kでの比熱容量は25.86 J/(mol·K)。標準状態での密度は21.45 g/cm³に達し、白金は自然界で最も密度の高い元素の一つに位置づけられる。熱伝導率は71.6 W/(m·K)、293 Kでの電気伝導率は9.43 × 10⁶ S/mである。
化学的性質と反応性
電子構造と結合特性
白金のd⁹電子配置は−2から+10までの多様な配位幾何構造と酸化状態を可能にするが、安定な化合物では+2と+4が主である。部分的に満たされたd軌道は特にピアソンの硬軟酸塩基理論に基づく軟電子供与原子との強い配位結合を促進する。Pt(II)錯体はd⁸系の結晶場安定化効果により平面四角形構造を特徴とする。結合形成にはd軌道の寄与が顕著で、結合解離エネルギーが頻繁に300 kJ/molを超えるPt-配位子相互作用を生成する。有機金属錯体でのPt-C結合は約536 kJ/molの強度を持つ。この金属は反位効果(trans effect)が顕著で、置換反応メカニズムや錯体の安定性に影響を与える。
電気化学的および熱力学的性質
電気陰性度はポーリング基準で2.28、オールド-ロチョウ基準で2.25と中程度の電子吸引能力を示す。標準還元電位は酸化状態に大きく依存し、Pt²⁺/PtはE° = +1.118 V、PtCl₄²⁻/PtはE° = +0.755 Vである。PtO₂/Ptカップルは標準条件でE° = +1.045 Vを示す。電気化学系列における位置は白金の貴金属性と酸化溶解抵抗性を確立する。熱力学的安定性は主な二元化合物の生成エンタルピーが負であることで示され、PtOはΔfH° = −80.3 kJ/mol、PtO₂はΔfH° = −123.4 kJ/molである。逐次イオン化エネルギーは870 kJ/mol、1791 kJ/mol、2800 kJ/molと系統的に増加する。
化学化合物と錯形成
二元および三元化合物
白金は多様な化学量論比と構造配置を持つ二元化合物を形成する。白金酸化物には酸化還元両性特性を示すPtO(テンナイト構造)とPtO₂(ルチル構造)が含まれる。ハロゲン化物はPtF₂からPtI₄までの全系列を網羅し、四面体構造のPtF₆が最高のフッ化物酸化状態を示す。クロロ白金酸塩は特に重要な化合物群で、ヘキサクロロ白金酸H₂PtCl₆と各種アルカリ金属塩が含まれる。硫化物には天然鉱物で一般的なPtS(コウパー鉱構造)とPtS₂が含まれる。三元系にはペロブスカイト構造のBaPtO₃や層状構造のK₂PtCl₄など、白金の複雑な酸化物・ハロゲン化物フレームワークにおける多様性が示される。
配位化学と有機金属化合物
白金は単純なイオンから複雑な有機分子まで多様な配位子との広範な配位化学を示す。一般的な配位数は2、4、6で、Pt(II)種では平面四角形構造が優勢である。初期の有機金属化合物の例として、Zeise's塩K[PtCl₃(C₂H₄)]·H₂Oが挙げられる。ホスフィン錯体はPt-P結合長約2.31 ÅのPtCl₂(PPh₃)₂など極めて高い安定性を示す。窒素供与配位子はcisplatin cis-[PtCl₂(NH₃)₂]のように抗癌活性を持つ安定な錯体を形成する。有機金属白金化合物は単純なアルキル錯体から複雑なメタラサイクルまで多様な構造を包含する。触媒活性種は頻繁にホスフィンまたは窒素含有配位子を含み、基質の配位とその後の変換を通じて活性化を促進する。
天然存在と同位体分析
地球化学的分布と存在比
白金の地殻存在比は約5 μg/kg(5 ppb)と極めて低く、地球で最も希少な元素の一つに分類される。地球化学的特性は siderophile(親鉄元素)性を反映し、惑星分化プロセス中に金属相への強い親和性を示す。主要産地はマグマ分異作用によるマフィック・超マフィック火成複合体、特に南アフリカのブッシュフェルド複合体とモンタナ州のスティルウォーター複合体に集中している。ブッシュフェルド複合体のMerensky Reefには全球埋蔵量の約75%がマグマ分異作用によって濃集されている。コロンビアやウラル山脈で歴史的に重要だった砂鉱床は原鉱床の風化・侵食によって形成される。現代の生産統計では南アフリカが全球生産の約70%、ロシアが15%、北米が10%を占めている。
核特性と同位体組成
天然白金は6つの安定同位体から構成される:¹⁹⁰Pt(0.012%)、¹⁹²Pt(0.782%)、¹⁹⁴Pt(32.967%)、¹⁹⁵Pt(33.832%)、¹⁹⁶Pt(25.242%)、¹⁹⁸Pt(7.163%)。¹⁹⁵Ptは核スピンI = 1/2と磁気モーメントμ = 0.6095核磁子を持ち、NMR分光法への応用を可能にする。¹⁹⁰Ptは半減期4.83 × 10¹¹年のアルファ崩壊を起こし、天然白金試料で16.8 Bq/kgの放射能を示す。同位体間で中性子吸収断面積が大きく異なり、¹⁹⁵Ptの熱中性子吸収断面積は27.5 バーンである。合成同位体は¹⁶⁵Ptから²⁰⁸Ptまで存在し、放射性同位体中最長半減期50年の¹⁹³Ptが特徴的である。核応用では特定同位体が研究・医療用途に利用され、特に放射線療法プロトコルで重要である。
工業生産と技術応用
抽出および精製方法
白金の主抽出は硫化物含有鉱石の採掘と複雑な冶金プロセスを伴う。初期濃縮ではフロス選鉱により、通常3-10 g/tの原鉱から100-300 g/t PGMsへの濃縮が達成される。1500°Cを超える温度での製錬は銅-ニッケル-PGM合金を含むマットを生成する。その後の加圧浸出と溶媒抽出により基礎金属から白金族元素を分離する。最終精製では王水溶解と選択的沈殿・還元プロセスを採用する。工業スケールでの生産は多段階の精錬により99.95%を超える純度を達成する。年間全球生産量は190トンに迫り、処理効率は通常鉱石中の白金の85-95%を回収する。環境配慮として硫酸および硝酸ガスの管理が特に重要である。
技術応用と今後の展望
自動車用触媒コンバーターは白金生産量の約45%を消費し、優れた酸化・還元触媒機能を発揮している。石油精製用途は9%を占め、主にナフサを高オクタン価ガソリンに転換する触媒改質プロセスに使用される。宝飾用途は34%の需要を占め、白金の耐久性と変色抵抗性を活かしている。新興用途には水素エネルギーシステムの燃料電池技術があり、白金は酸素還元および水素酸化反応を極めて効率的に触媒する。電子用途ではハードディスクドライブ部品や特殊接点に化学的安定性と電気伝導性を活かす。医療用途は医薬合成の触媒機能とcisplatinやcarboplatinなどの抗癌剤の直接使用を含む。今後の技術開発は触媒用途での白金使用量削減と性能維持の両立に焦点を当てる。
歴史的発展と発見
考古学的証拠は現在のエクアドルとコロンビアで前コロンブス期文明が粉末冶金技術で白金-金合金製品を作成していたことを示す。ヨーロッパでの認識は1557年にジュリウス・カエサル・スカリガーがダリエン地方の未知の貴金属を記載したのが始まりである。スペインの植民地支配者は白金を金鉱中の不純物と見なし、通貨用途での使用を禁止した。科学的調査は1735-1748年の南米探査後にアントニオ・デ・ウロアが1748年に発表した最初の詳細記載から始まった。1750年のロイヤル協会でのウィリアム・ブラウンリッグの発表は白金の化学的同定を確立した。1780年代にピエール=フランソワ・シャバノーが最初の成功した純化と展延性白金金属の加工を達成した。元素名はスペイン語の「platina」(「plata」(銀)の愛称形)に由来し、銀白色の外観を反映している。現代的理解はシェーファーやベルグマン、ベルツェリウスなどの化学者の貢献により18-19世紀に発展した。
結論
白金の化学的不活性、触媒活性、物理的耐久性のユニークな組み合わせにより、現代技術と産業において不可欠な位置を占めている。d⁹電子配置は多様な配位化学を可能にしつつ、過酷な条件での卓越した安定性を維持する。工業応用は新エネルギー技術や環境保護システムで継続的に拡大している。今後の研究は供給制約と経済的要因から、白金消費量を最小化しつつ触媒効率を最大化することを目指す。高度な合成法とナノテクノロジーの応用により、燃料電池や公害制御、化学合成用途での性能向上が期待されている。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
