| 元素 | |
|---|---|
79Au金196.96656942
8 18 32 18 1 |
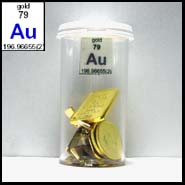
|
| 基本的なプロパティ | |
|---|---|
| 原子番号 | 79 |
| 原子量 | 196.9665694 amu |
| 要素ファミリー | 遷移金属 |
| 期間 | 6 |
| グループ | 1 |
| ブロック | s-block |
| 発見された年 | 6000 BC |
| 同位体分布 |
|---|
197Au 100% |
| 物理的特性 | |
|---|---|
| 密度 | 19.282 g/cm3 (STP) |
(H) 8.988E-5 マイトネリウム (Mt) 28 | |
| 融点 | 1064.58 °C |
ヘリウム (He) -272.2 炭素 (C) 3675 | |
| 沸点 | 2940 °C |
ヘリウム (He) -268.9 タングステン (W) 5927 | |
| 化学的性質 | |
|---|---|
| 酸化状態 (あまり一般的ではない) | +3 (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +5) |
| 第一イオン化エネルギー | 9.225 eV |
セシウム (Cs) 3.894 ヘリウム (He) 24.587 | |
| 電子親和力 | 2.309 eV |
ノーベリウム (No) -2.33 (Cl) 3.612725 | |
| 電気陰性度 | 2.54 |
セシウム (Cs) 0.79 (F) 3.98 | |
金 (Au): 周期表の元素
要約
金 (Au) は原子番号79を持つ典型的な貴金属で、酸化および腐食への極めて高い耐性が特徴です。この元素は特有の黄色い金属光沢を示し、面心立方構造で結晶化し、密度は19.3 g/cm³です。金は優れた展性と延性を持ち、単原子線や超薄箔の形成が可能です。化合物中では主に+1および+3の酸化状態を示しますが、特定条件下では-1から+5の異常な状態も存在します。金の電子親和力222.8 kJ/molは金属中最高値で、化学的貴金属性に寄与しています。地殻中での存在量は約40億分の1と希少ですが、集中鉱床によりシアン化物浸出および火法冶金プロセスで経済的な抽出が可能です。工業応用では電子伝導性、化学的不活性、光学特性が電子機器、触媒、特殊材料で活用されています。
序論
金は周期表第11族の6周期目に位置し、白金と水銀の間にあります。銅および銀と共に造幣金属に属し、d10s1電子配置により独特な化学・物理的性質を示します。遷移金属系列における位置は、相対論的効果が原子の性質および化学結合に大きな影響を与える後期dブロック元素に属します。
金の発見は有史以前に遡り、考古学的証拠によれば紀元前5千年紀には天然金が使用されていました。古代文明は金の不変性を認識し、永久性および神聖な属性と結びつけていました。元素記号Auはラテン語の「aurum(曙色)」に由来し、他の貴金属とは異なる特有の黄金色の輝きを反映しています。
現代の金化学理解はその錯体、電気化学的性質、冶金特性の体系的な研究を通じて進展しました。現在の研究はナノ構造金材料、触媒応用、生体適合性技術に焦点を当てています。化学的安定性と生物学的適合性の組み合わせにより、これらの分野での価値が増しています。
物理的性質および原子構造
基本的な原子パラメータ
金の原子番号は79で、標準原子量は196.966570 ± 0.000004 uです。周期表の中でも特に正確に決定された原子量の一つです。電子配置は[Xe] 4f14 5d10 6s1で、第11族の特徴を示します。満電子d軌道は特別な安定性を与えつつ、単一のs電子が化学結合に利用可能です。
金化学においては、高核電荷とそれに伴う内殻電子の高速運動により相対論的効果が顕著です。6s軌道の収縮と5d軌道の膨張により、軽い同族体とは異なる化学的性質が生じます。6s軌道の安定化により、金は化学反応に参加しにくく、貴金属性の理由となっています。
原子半径は金属半径144 pm、共有半径137 pmです。イオン半径は酸化状態と配位環境に強く依存し、Au+は四面体配位で137 pm、Au3+は平面四角形配位で85 pmです。これらの寸法パラメータは、酸化による核電荷の影響が電子間反発を凌駕する際の収縮を示しています。
巨視的物理特性
金の明るい黄色い金属外観は、約470 nmの青色光波長を特異的に吸収する結果です。この色調は5d軌道と6s軌道のエネルギー差が相対論的効果で低下し、可視光吸収が可能になるため生じます。この独特な色合いにより、銀や他の貴金属と区別されます。
結晶構造は室温で面心立方格子で、格子定数a = 407.82 pmです。この密充填構造は原子配位を最大化しつつ系のエネルギーを最小化し、20℃での密度19.32 g/cm³を生み出します。緻密な充填構造により、金は優れた機械的特性を持ち、0.1 μmの箔や単原子線に加工可能です。
熱的特性は融点1064.18℃、沸点2970℃で、結晶格子内の強金属結合を反映しています。融解熱は12.55 kJ/mol、蒸発熱は324 kJ/molです。25℃での定圧比熱容量は25.42 J/(mol·K)です。熱伝導率317 W/(m·K)により、銅や銀ほどではないものの良好な熱伝導体です。
20℃での電気伝導率は45.2 × 106 S/mで、銅の約70%です。この中程度の値ながら、優れた腐食耐性により長期信頼性が求められる電気接続に不可欠です。電気抵抗率は温度と共に線形増加し、0.0034 K-1の温度係数を持ちます。
化学的性質および反応性
電子構造および結合特性
金化学は+1および+3酸化状態を中心に展開します。6s電子の容易な放出と、5d10構造へのアクセス困難性が反映されています。Au+イオンはd10電子構造により、直線配位幾何学を示すことが多いです。例としてシアン錯体[Au(CN)2]-や金(I)ハロゲン化物があります。
金(III)化合物はd8電子構造により、配位子場効果で平面四角形配位を好む傾向があります。金(III)塩化物AuCl3や窒素、リン、硫黄供与配位子との錯体でこの配位が観察されます。Au(III)錯体の結合長は190-210 pmの範囲です。
金化合物の共有結合は、金の高電気陰性度(パウリングスケールで2.54)により顕著なイオン性を持ちます。このため電気陰性元素との化合物が安定で、金が陰イオンとして機能するアウリドも存在します。金属金中のAu-Au結合エネルギーは約226 kJ/molで、相対論的効果で安定化された金属結合を反映しています。
電気化学的および熱力学的性質
金の標準還元電位は非常に正で、酸化抵抗を示します。Au3+/Au系ではE° = +1.498 V、Au+/Au系では+1.692 Vです。これらの高正値は、金の酸化に極めて強力な酸化条件が必要であることを示し、最貴金属としての分類に合致しています。
逐次イオン化エネルギーは化学反応性に影響を与えます。第一イオン化エネルギーは890.1 kJ/molで6s1電子の放出を反映し、第二イオン化エネルギーは1980 kJ/molに跳ね上がります。第三イオン化エネルギー2900 kJ/molにより、Au3+化合物の共有性が顕著で、高酸化状態の希少性が説明されます。
金の電子親和力222.8 kJ/molは金属中最高値で、多くの非金属に匹敵します。この値により、セシウムアウリドCsAuのような化合物で金が-1酸化状態を持つ陰イオンを形成可能です。相対論的効果で収縮した6s軌道が、軽い同族体より追加電子密度を保持しやすくなります。
金化合物の熱力学的安定性は酸化状態および配位子環境で大きく変化します。d10構造の保持により、金(I)化合物は金(III)種より安定です。金(III)化合物は加熱で分解し、金(I)種または金属金を生成します。AuCl3は160℃以上で分解します。
化合物および錯体形成
二元および三元化合物
金は化学的貴金属性により、多くの非金属と二元化合物を形成しますが、高温や特殊合成条件が必要です。金(I)ハロゲン化物は直線配位のポリマー状ジグザグ鎖構造を持ちます。金(I)塩化物AuClは、3AuCl → AuCl3 + 2Auの不均化反応で平衡状態にあります。
金(III)ハロゲン化物はより安定で構造モチーフも異なります。金(III)塩化物は気相では二量体Au2Cl6を形成しますが、固体ではポリマー構造を示します。水中で加水分解し、クロロオーリック酸HAuCl4を生成します。これは金化学および電気めっき応用で重要な試薬です。
金の酸化物形成は困難です。金(III)酸化物Au2O3は水酸化金(III)の脱水で合成されますが、160℃以上で分解します。この熱的不安定性は標準状態での正の生成自由エネルギー(+80.8 kJ/mol)によるものです。
硫化物には金(I)硫化物Au2Sおよび金(III)硫化物が含まれ、いずれも希少な鉱物として存在します。金二硫化物AuS2は高温高圧下で硫黄と反応して形成されます。これらの硫化物は酸化物より安定で、ピアソンの硬軟酸塩基理論による金の軟酸特性と硫黄の軟塩基性が一致するためです。
配位化学および有機金属化合物
金の配位化学は、ほぼすべての供与原子種との錯体形成を含みますが、硬軟性に基づく選択性があります。金(I)はホスフィン、チオエーテル、シアン化物などの軟供与配位子と安定な二配位直線錯体を形成します。特に重要なのは金鉱石のシアン化物浸出で活性種となるジシアノaurate(I)陰イオン[Au(CN)2]-です。
金(I)ホスフィン錯体は構造多様性と顕著な安定性を持ちます。単純な[Au(PPh3)Cl]は直線配位を示し、橋かけ種[Au2(μ-dppm)2]2+は金-金相互作用を示します。これらのアウロフィル相互作用は270-350 pmの距離で発現し、共有結合より長くファンデルワールス接触より短く、金(I)系の構造組織化に寄与します。
金(III)配位化学は通常4配位の平面四角形構造が中心ですが、特殊条件下では5・6配位の例も存在します。ピリジンを含む[AuCl3(py)]やビピリジンなどのキレート配位子との錯体はπ-受容能が安定性に与える影響を示しています。
有機金属金化学は触媒活性種の発見により急速に進展しました。金(I)錯体はアルキン活性化、環状異性化、炭素-炭素結合形成を独特な活性化モードで触媒します。例として[(Ph3P)AuCl]やN-ヘテロ環状カルベン(NHC)配位子を含む[Au(NHC)Cl]があり、これらは卓越した安定性と調整可能性を提供します。
天然存在および同位体分析
地球化学的分布および存在量
金の地殻存在量は重量比で40億分の1と極めて低く、地球の形成初期に親鉄性により大部分が地核に移行したためです。残存する金は熱水プロセスで経済的な濃度で輸送・堆積されます。海水には13兆分の1の金が含まれ、世界全体で約2000万トンの蓄積がありますが、極度の希釈により経済的な抽出は困難です。
海底堆積物では、特に活発な熱水噴出域で金は他の硫化鉱物と共に濃縮されます。金は自然界では主に単体で存在しますが、カランバイトAuTe2やシルバナイト(Au,Ag)Te2などのテルル化物鉱物も重要な鉱石です。天然金は主に銀を不純物として含み、純金から銀50%を含むエレクトルムまで合金組成が変化します。
金塊鉱床は原生金含有岩石の風化・侵食により形成され、高密度により川底堆積物に蓄積されます。これらの二次鉱床は重力分離技術で歴史上多くの金を供給しました。著名な金塊地域にはカリフォルニア金ブーム鉱床、クロンダイク金鉱山、金粒子が微細なフラクから数kgのナゲットに至るアフリカの河川系があります。
核的性質および同位体組成
金は自然に197Auという単一安定同位体のみ存在します。質量数197は79個の陽子と118個の中性子を含み、核スピンI=3/2、磁気モーメントμ=+0.148核磁子です。これらの性質は金化合物のNMR研究に利用されます。単一同位体性質は分析化学を簡素化し、正確な原子量決定を可能にします。
人工金同位体は質量数169-205を含み、半減期はマイクロ秒から数年までです。特に重要な放射性同位体198Auは2.695日の半減期でβ崩壊し、安定な198Hgになります。この同位体は核医学でがん治療に応用され、198Au標識金ナノ粒子が腫瘍部位へのターゲット放射線治療に用いられます。
金-195(半減期186.1日)は電子捕獲で195Ptに崩壊し、医療応用に適しています。研究用途では、冶金および地球化学のトレーサー研究で短寿命同位体が利用され、複雑系での金挙動追跡に貢献します。
中性子活性化分析は、熱中性子捕獲断面積σ=98.65バーンを活かし、安定な197Auから198Auを生成します。この技術は地質・環境試料で10億分の1以下の検出感度を達成します。高断面積は原子炉環境での金部品に十分な遮蔽対策を求めるため、重要な特性です。
工業生産および技術応用
抽出および精製方法
現代の金抽出はシアン化物浸出が主流です。金はシアン錯体を形成し溶解します。基本反応式:4Au + 8CN- + O2 + 2H2O → 4[Au(CN)2]- + 4OH-。効率的な溶解にはpH10.5以上、シアン濃度200-500 mg/L、空気ばらまきによる溶存酸素管理が必須です。
金鉱石のパイル浸出では、不浸透性パッド上に鉱石を積載し希薄シアン溶液を灌漬します。金回収効率は鉱石鉱物学および粒子径分布により60-90%です。抽出液は活性炭吸着で金を濃縮し、その後溶離および電解抽出で回収します。
高品位鉱石およびコンセントレートには火法冶金が重要です。1200℃超の電気炉または燃料炉での溶融処理により、金は脈石鉱物から分離されます。ドレーバーは金含有量80-95%で、還元反応に適した化学環境を提供する助溶剤添加で効率が向上します。
高純度精製にはヴォールヴィル電解法またはミラー塩素化法が用いられます。ヴォールヴィル法は粗金アノードと純金カソードでクロロオーリック酸溶液を電解し、99.99%超の純度を達成します。ミラー法は1100℃での溶融金に塩素ガスを処理し、不純物金属を揮発性塩化物として除去し、約99.5%純度の金を生成します。
技術応用および将来展望
電子機器応用では電気伝導性、腐食耐性、環境耐性の組み合わせが活かされます。半導体ワイヤーボンディングでは15-50 μm径の金線がICチップとパッケージリードを接続します。金-シリコン結合は熱サイクルや経年劣化に耐え、代替材料を凌駕する信頼性を提供します。
プリント基板では、信頼性が要求される接点、コネクタピン、エッジフィンガーに金めっきが利用されます。一般的なめっき厚さはニッケル拡散防止層上に0.5-2.5 μmです。浸漬金めっきは金塩化物と銅の置換反応を利用し、複雑形状への均一被覆を経済的に実現します。
触媒応用は急速に成長する技術分野です。5 nm未満の金ナノ粒子は、量子サイズ効果により電子構造が変化し、分子活性化に極めて活性なサイトを提供します。一酸化炭素酸化触媒では二酸化チタンや酸化鉄上に担持された金粒子が利用されます。
医療応用では生体適合性と光学特性が診断および治療に応用されます。金ナノ粒子は表面修飾により特定細胞標的に薬物送達を可能にします。フォトサーマル療法では近赤外吸収性金ナノロッドががん治療用局所加熱を提供し、金ベースのコントラスト剤はCTや光学干渉断層(OCT)の画像診断を強化します。
新技術開発では再生可能エネルギーシステム、量子エレクトロニクス、先進材料に金の潜在能力が探求されています。プラズモニクス応用では金ナノ構造が光を波長以下のスケールで制御し、太陽電池効率向上や新規光学デバイスを可能にします。金系超伝導デバイス、単原子触媒、有機-無機ハイブリッド材料の研究が継続され、金の独特な特性が新機能を実現しています。
歴史的発展および発見
金の発見は有史以前に遡り、考古学的証拠からブルガリアのヴァルナ古墳(紀元前4600-4200年)に金製品が存在します。初期の金工芸品は合金化、成形、装飾技術を示し、金と富・永久性の結びつきを確立しました。古代エジプト文明は儀礼用具、装飾品、建築要素に金を多用し、墓壁画には採掘・精製技術が描かれています。
古典古代では金の化学的不活性が認識され、ローマ文献は火および腐食耐性を記述しています。「aurum」のラテン語名は、プロトインドヨーロッパ語源の「曙色」に由来し、金属中で特異な輝きを反映しています。中世の錬金術師は金の転換実験を通じて基礎化学技術を開発しました。
18-19世紀に金化学は体系的化合物研究で進展しました。アントワーヌ・ラヴォアジエは金を元素と確立し、後続研究者が金塩、錯体、電気化学的性質を詳細に記述しました。王水による金溶解技術の発展は分析・精製に不可欠な能力を提供しました。
20世紀の配位理論、電子構造理解、分析技術の進展により現代金化学は深化しました。アルフレッド・ウェルナーの配位理論が錯体構造を説明し、X線結晶構造解析が詳細な構造情報を提供しました。現在の研究は触媒、ナノテク、材料科学で拡大し、古代金属が化学革新の最前線に留まることを示しています。
結論
金は周期表内で相対論的効果による独特な電子特性と酸化抵抗で貴金属性の典型です。特有のd10s1配置により直線金(I)および平面四角形金(III)錯体形成能力を持ち、異常酸化状態の探索により遷移金属化学の境界を拡張しています。高電子親和力と正の還元電位は化学反応抵抗性を定量化しますが、軟供与配位子との豊かな配位化学も示します。
金の工業的意義は装飾品・通貨から電子機器、触媒、医療技術へと拡大しています。腐食耐性と電気伝導性の組み合わせにより、重要な電子接続に不可欠です。新規触媒応用では金ナノ粒子の量子サイズ効果により、反応選択性および効率が飛躍的に向上しています。
将来の研究は単原子触媒、プラズモニックデバイス、医療応用に焦点を当て、安定性、導電性、生体適合性の組み合わせにより革新的技術を実現します。金化学における相対論的効果の理解は、他の重元素研究にも貢献し、周期表全体の結合・反応性理論枠組みの深化に寄与し続けています。

化学反応式の係数調整サイトへのご意見·ご感想
